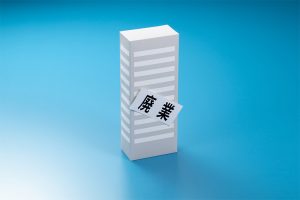再生型M&Aによる事業再生とは?メリットやスキームを解説

再生型M&Aとは、企業再生を目的に実施するM&Aを指します。複数のスキームがあり、それぞれ期待できる効果が異なります。
企業の成長や市場拡大を目的とする一般的なM&Aとは異なる特徴があるため、メリットやデメリット、成功させるポイントなどを事前に把握しておくことが大切です。
このコラムでは、再生型M&Aの具体的な手法やメリット・デメリット、押さえておくべきポイントや成功事例などを紹介します。
再生型M&Aとは?
再生型M&Aとは、企業再生を目的に実施するM&Aのことです。債務整理や事業整理にM&A手法を活用することにより、企業再生を目指します。
再生型M&Aの対象となるのは「債務超過や経営利益が赤字」「銀行借入れの返済が滞っている」といった、経営不振に陥っている企業です。
企業の成長や市場拡大を目的とする一般的なM&Aの場合、買い手企業・売り手企業・M&A会社(FAなど)が関与します。一方、企業の再建を目指す再生型M&Aでは債権者(金融機関)も大きく関係することが特徴です。
再生型M&Aのメリット
再生型M&Aには、以下のようなメリットがあります。
- スポンサー企業から支援を受けられる
- 状況に応じた手法を選べる
- 成功すれば廃業を回避できる
各メリットについて解説します。
スポンサー企業から支援を受けられる
再生型M&Aの1つめのメリットは、スポンサー企業から支援を受けられる点です。
企業再生には、債務弁済や人員整理などの事業整理コスト、システムなどの分離コストなどに対する資金が必要です。
しかし、費用面の負担が大きいため、自力での再建は容易ではありません。「保有資産を現金化して債務返済に充当しても返済しきれない」というケースもみられます。
再生型M&Aによってスポンサーから資金援助を受けたり、経営資源を活用したりすることで、効率的に事業再建を図ることが可能です。
状況に応じた手法を選べる
状況に応じた手法を選べる点も、再生型M&Aのメリットにあげられます。
再生型M&Aには複数の手法があり、それぞれ効果が異なります。会社の状況に応じた適切な方法を選んで企業再生を図ることが可能です。たとえば「会社分割方式と第二会社方式を比較検討し、負債の引き継ぎリスクを考慮して最適な方を選択する」といった選び方もできるでしょう。
なお、再生型M&Aの具体的なスキームについては後述します。
成功すれば廃業を回避できる
再生型M&Aが成功すれば、廃業を回避し、会社や事業を存続させることが可能です。事業を譲渡することで存続が叶えば、従業員の雇用や取引先を維持でき、技術やノウハウの喪失リスクも抑えられます。
必ずしも成功するとは限らないとはいえ、廃業を回避したい企業にとって、再生型M&Aは検討の価値がある手段の1つといえるでしょう。
再生型M&Aのデメリット
再生型M&Aには、以下のようなデメリットもあります。
- 通常のM&Aよりも難易度が高い
- 経営者にとってシビアな状況になりやすい
各デメリットについて解説します。
通常のM&Aよりも難易度が高い
1つめのデメリットは、通常のM&Aよりも難易度が高い点です。
再生が困難な企業を対象とする再生型M&Aは、通常のM&Aと比べて難易度が高いケースが多く、スムーズに最適な買い手企業が見つかるとは限りません。
また、債権者との交渉や煩雑な法的手続きが必要なため、高度な知識が求められます。取引に時間がかかれば、多くの労力を要します。
基本的に自社のみでの対応は難しいため、専門家のサポートを受けることがおすすめです。
経営者にとってシビアな状況になりやすい
経営者にとってシビアな状況になりやすい点も、再生型M&Aのデメリットにあげられます。通常のM&Aとは異なり、「引退しながら現金を受け取れる」といった旨みのあるスキームではないためです。
自己破産を回避できる代わりに、「すべての個人資産を債務の返済に充てる」というケースも珍しくありません。株式会社は原則として有限責任であるものの、中小企業やオーナー企業の場合、以下のような理由で経営者個人が責任を負う可能性があります。
- 銀行から融資を受ける際、経営者による個人保証をつけている場合
- 経営者が会社の借入金に対する連帯保証人となっている場合
- 経営者が個人資産から会社に貸し付けている場合
再生型M&Aを希望する経営者は、自身にとって厳しい状況になる可能性も考慮しておく必要があるでしょう。
再生型M&Aの代表的な4つのスキーム
再生型M&Aには、主に以下の4つのスキームがあります。
- 企業再生方式
- 事業譲渡方式
- 会社分割方式
- 第二会社方式
それぞれ詳しく解説します。
1.企業再生方式
企業再生方式とは、スポンサー企業の子会社として再生を図るスキームです。スポンサー企業から資金提供を受け、債務超過の解消と成長を目指します。
会社の法人格を維持した状態で採算事業をメインに企業再生を目指す手法であり、「私的再生手続きによる実施が可能であること」が他の再生型M&Aとの相違点です。
企業再生方式はスポンサー企業の経営資源を共有できるメリットがある一方、中小企業には不向きと言わざるを得ません。スポンサー企業にとっては、事業の取引規模が小さい中小企業の再生に成功したとしても、得られる利益は少ないとみなされやすいためです。
債務が免除されたときに発生する「債務免除益」に課される税金は、「繰越欠損金」と相殺可能です。たとえば1億円の債務免除益が課されても、過去の赤字が1億円ある場合は相殺して利益ゼロとみなし、税金をゼロにできます。
規模が小さい企業では繰越欠損金が少ないケースが多く、スポンサー企業にとっては債務免除益との相殺メリットを活かしにくい傾向があります。
そのため、中小企業の再生型M&Aに企業再生方式が採用される可能性は低いでしょう。
2.事業譲渡方式
再生型M&Aにおける事業譲渡方式とは、採算事業を中心に、スポンサー企業の一事業として再建する手法です。
たとえば「利益を上げている事業はあるものの、不採算事業が経営全体に負担をかけており、赤字に陥っている」といったケースでは、不採算事業の清算による企業再生を期待できるでしょう。
事業譲渡方式の場合、不採算事業は不要な事業などを譲渡して得られた資金などを元に清算を行います。事業譲渡の対価を債務弁済に充てられるほか、破産手続きになった場合でも利用可能というメリットがあり、中小企業の再生型M&Aとして広く活用されています。
3.会社分割方式
会社分割方式とは、採算事業を別会社に移転させ、残った不採算事業の再建を目指す手法です。
採算事業と不採算事業を早期に切り離すことで採算事業を保護し、債権者の協力を得ながら再建を目指すことによって不採算事業のさらなる業績悪化を回避する狙いがあります。
たとえば採算事業を新設会社に引き継げば、債務を抱えていない優良企業として、スポンサー企業からの融資を受けやすくなります。潤沢な資金を確保できれば事業の安定・成長につながるため、早期の企業再生を図ることが可能です。
ただし、負債を抱えた不採算事業の立て直しは難易度が高いため、再建ではなく清算となるケースが多いのが実情です。
4.第二会社方式
第二会社方式とは、採算事業のみを他の新設会社(第二会社)に引き継ぎ、負債は債務者企業(旧会社)に残す手法です。
旧会社は不採算事業を自社株式や遊休資産の売却で清算し、法人格を消滅させます。
第二会社は親族や社員などの身内が新設するケースもあれば、スポンサー企業が新会社を設立するケースもあります。
切り離した採算事業に経営資源を集中させて効果的な成長・再建を図れることから債権回収率が高まるため、債権者やスポンサーからの協力を得やすいことが特徴です。
不採算事業を切り離すため、第二会社では効率よく事業再建を進めやすいメリットがあります。
再生型M&Aの基本的な流れ
再生型M&Aの基本的な流れは、以下のとおりです。
- 再生計画を策定する
- 金融機関と調整する
- スポンサーを選定する
- 基本合意を締結する
- デューデリジェンスを実施する
- 最終契約を締結する
- クロージング手続きを行う
経営改善が重視される再生型M&Aでは、金融機関との関係性を考慮しなければならない分、通常のM&Aよりも工程が複雑になりやすい傾向があります。
自社対応が難しい場合、M&Aの実績がある仲介会社などの専門家に相談しましょう。
再生型M&Aを成功させるためのポイント
M&Aを実行しつつ事業再生も図る再生型M&Aは、通常のM&Aよりも手続きが煩雑で時間も手間もかかりがちです。スポンサー企業を見つけ、交渉を進める難易度も高い傾向があります。
再生型M&Aの成功率を高め、スムーズに進めるためには、専門家のサポートを受けることが大切です。
ただし、税理士や公認会計士といった専門家であっても、再生型M&Aに明るいとは限りません。再生型M&Aを検討する場合、M&Aを専門的に支援する仲介会社のサポートを受けるとよいでしょう。
まとめ
再生型M&Aとは、企業再生を目的に実施するM&Aを指します。スポンサー企業から支援を受けられ、成功すれば廃業を回避することが可能です。会社の状況に応じて手法を選べるメリットもあります。
一方、通常のM&Aに比べて難易度が高くなりやすいデメリットもあります。再生型M&Aをスムーズに進めるためには、専門家による的確なサポートを受けることが大切です。まずは、M&Aの実績がある仲介会社に相談してみるとよいでしょう。
人気の記事

投稿日:2024年08月23日更新日:2025年06月06日
地位承継とは?意味や継承との違い、使い分けなどを解説
- #ニュース・コラム
- #スキーム
- #ニュース・コラム
- #スキーム
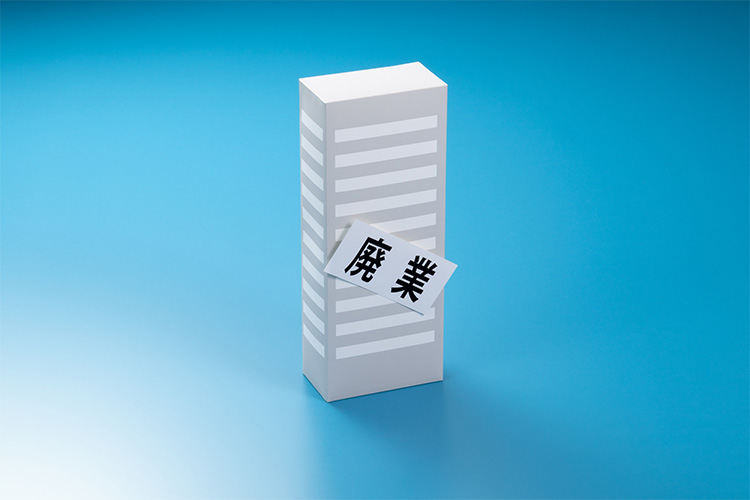
投稿日:2025年01月09日更新日:2025年06月06日
会社をたたむ費用はいくら?廃業手続きの流れも解説
- #ニュース・コラム
- #廃業
- #ニュース・コラム
- #廃業

投稿日:2024年06月03日更新日:2025年06月06日
M&Aのディールとは?一連のプロセスと成功につながる4つの秘訣
- #ニュース・コラム
- #M&Aの流れ
- #ニュース・コラム
- #M&Aの流れ
#カテゴリ・タグ一覧
まずはお気軽にご相談ください
※秘密厳守でご対応します。
幅広い業種の案件を成約させたプロの
メンバーが丁寧にご対応します。