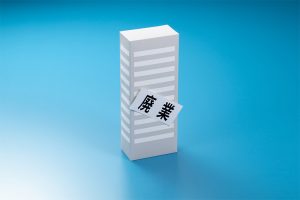キーマン条項(ロックアップ)とは?M&A契約時のポイントも解説

キーマン条項とは、M&Aを実施してからも、売り手の経営者などを一定期間対象会社に在籍させるための契約条項を指します。M&A後の引き継ぎをスムーズに進めることが、キーマン条項を設ける主な目的です。
キーマン条項を設定することのデメリットとして、対象者がすぐにリタイアできないことや、モチベーションが低下することなどがあげられます。そのため、設定期間を十分に考慮することが大切です。
このコラムでは、キーマン条項を設ける理由や、契約時のポイントについて詳しく解説します。
M&Aのキーマン条項(ロックアップ)とは
キーマン条項(Keyman Clause)とは、円滑に引き継ぎを実施することなどを目的に、M&A後も一定期間重要人物を対象会社に在籍させることを定める条項のことです。ロックアップ(Lock Up)と表現することもあります。
キーマン条項の対象となるのは、売り手の代表者や役員、事業運営の中心を担う従業員などです。具体的な期間は、契約内容によって異なります。
M&Aでキーマン条項を設ける理由
M&Aでキーマン条項を設定する理由について、売り手側・買い手側の観点からそれぞれ解説します。
売り手側
売り手があえて契約にキーマン条項を設けようとする主な理由は、売却交渉をスムーズに進めたり、高値での売却につなげたりするためです。経営陣がM&A実施後も数年間在籍して円滑に引き継ぎするよう努めることを伝えれば、買い手候補はM&Aに前向きになる可能性があります。
また、経営者が一定期間残ることで、M&Aに伴い不安な気持ちを抱えている従業員を安心させられるでしょう。さらに、M&Aで会社を売却してからも一定期間は役員報酬を得て収入を確保できることも、売り手がキーマン条項を望む理由のひとつにあげられます。
買い手側
キーパーソンをそのまま会社に在籍させてM&A実施後の引き継ぎをスムーズに進めるために、買い手は契約にキーマン条項を盛り込むことを望む場合があります。なぜなら、引き継ぎがうまくいかないと、M&A実施後すぐに事業を軌道に乗せることが困難なためです。
また、従業員のモチベーションが低下してM&A実施前後に離職することを防いだり、キーパーソンが有する技術やノウハウを活用して事業を成長させたりするために、キーマン条項を設定することもあります。
【売り手】キーマン条項を設けるデメリット
売り手にとって、キーマン条項を設けることのデメリットは、以下のとおりです。
- 違反すると損害賠償を請求されうる
- 新規事業を自由に立ち上げられないことがある
- すぐにリタイアできない
それぞれ解説します。
違反すると損害賠償を請求されうる
契約で定められた期間においてキーマン条項違反が発覚すると、損害賠償を請求されうる点が、売り手のデメリットです。
契約書には、違反した場合の罰則や対応について明記されることがあります。契約時は会社のために働き続けるつもりでも、事情が変わり期間内に辞めざるを得ないケースもあるため、安易にキーマン条項を盛り込まないことが大切です。また、病気で退職するケースなど、例外規定を設けられないかを契約前に交渉しましょう。
新規事業を自由に立ち上げられないことがある
売り手は、M&Aで多額の売却資金を得たとしても、キーマン条項が設定されている期間内に新規事業を自由に立ち上げられないことがある点もデメリットとしてあげられます。なぜなら、新たに立ち上げた会社とM&Aの対象会社に競合する部分があった場合に、競業禁止義務違反と捉えられかねないためです。
新規事業の立ち上げに限らず、競合他社への出資も制限される可能性があります。
すぐにリタイアできない
キーマン条項の対象に含まれる人は、すぐにリタイアできない点がデメリットです。
元々年齢や家族の事情などで会社から離れるためにM&Aを決意したとしても、キーマン条項がある限り数年間は対象会社で引き続き働かなければなりません。また、オーナー経営者の場合、M&A後は自分の会社でなくなるため、今までのような気持ちで働くことは難しくなるでしょう。
【買い手】キーマン条項を設けるデメリット
買い手にとって、キーマン条項を設定してもスムーズに引き継ぎしたり、うまく事業を成長させたりできない可能性がある点がデメリットです。
キーマン条項により引き続き対象会社に在籍することになった経営者は、以前のように高いモチベーションで業務を遂行できない場合があります。自分の会社ではなくなったこと、自分の考えで自由な経営ができないことなどが主な理由です。
キーマン条項を用いて前経営者を対象会社に止まらせても、モチベーションが低下していれば以前のような活躍は期待できないでしょう。
M&A契約でキーマン条項を設ける際のポイント
M&Aの契約において、キーマン条項を設ける際のポイントは、以下のとおりです。
- 契約相手が信頼できるか見極める
- アーンアウト条項を設けることも検討する
- 設定する期間を熟考する
- 双方で認識にズレがないよう調整する
- 専門家に相談する
ここから、各ポイントについて解説します。
契約相手が信頼できるか見極める
売り手でキーパーソンとして指定された人は、相手が本当に信用できる会社か見極めることがポイントです。M&A実施後も一定期間在籍しなければならないため、働きやすい環境が整っているのか確認しておきましょう。
一方、買い手もキーパーソンが信頼できる相手か見極めなければなりません。相手によっては、会社に在籍させても高いモチベーションで引き継ぎを進められない可能性があります。
アーンアウト条項を設けることも検討する
買い手は、引き継ぎをうまく進めるためにアーンアウト条項を設定することも検討しましょう。
アーンアウト条項とは、M&A後に対象事業が目標を達成した場合に、買い手が売り手に対して一定の報酬を支払うことを定めた条項です。アーンアウト条項を設定することにより、M&A後も対象会社のキーパーソンが高いモチベーションで業務を遂行することを期待できます。
なお、アーンアウト条項を設定する場合は、その分会社の売買価格を低く設定することがあるでしょう。
設定する期間を熟考する
キーマン条項として設定する期間を熟考することも必要です。売り手と買い手で話し合い、双方が納得できる期間に設定しましょう。
設定期間が長過ぎると、キーパーソンはなかなかリタイアできず、徐々にモチベーションが低下していく可能性があります。一方で、短過ぎると引き継ぎに十分な時間を確保できないでしょう。
一般的には、1〜3年でキーマン条項の期間を設定します。
双方で認識にズレがないよう調整する
双方で認識にズレが生じないようにすることも、キーマン条項を盛り込むうえで大切です。
とりあえずキーマン条項だけを設けて細かいことの記載は省くと、期間や義務の範囲などについて双方の考えが異なることがM&Aを実施してから判明し、トラブルに発展する可能性があります。契約前にお互い気になることを伝え、曖昧な部分をなくして契約書に明記しましょう。
専門家に相談する
キーマン条項の設定にあたっては専門知識が求められるため、専門家に確認することがポイントです。わからないまま相手が提案した文言をそのまま採用したり、インターネット上のフォーマットを修正せずに使ったりして契約書を作成すると、M&A実施後に自分が不利な状況に陥る可能性があります。
知識や経験を必要とする作業のため、キーマン条項の設定に限らず、M&A全般で専門家への相談を検討しましょう。
まとめ
M&A実施後の引き継ぎをスムーズに進めるために、買い手がキーマン条項の設定を希望する場合があります。売り手のキーパーソンも、キーマン条項を設定することで売却をスムーズに進められることがあるでしょう。
一方で、売り手はキーマン条項を設定すると自由にリタイアできなくなる点に注意が必要です。買い手も、キーマン条項があることでキーパーソンのモチベーションが低下する可能性を考えておかなければなりません。
そこで、キーマン条項を設定する際は、期間を熟考することやアーンアウト条項を検討することがポイントです。また、トラブルを防いだり、M&Aをスムーズに進めたりするために、事前に専門家に相談したうえでキーマン条項を盛り込むようにしましょう。
人気の記事

投稿日:2024年08月23日更新日:2025年06月06日
地位承継とは?意味や継承との違い、使い分けなどを解説
- #ニュース・コラム
- #スキーム
- #ニュース・コラム
- #スキーム
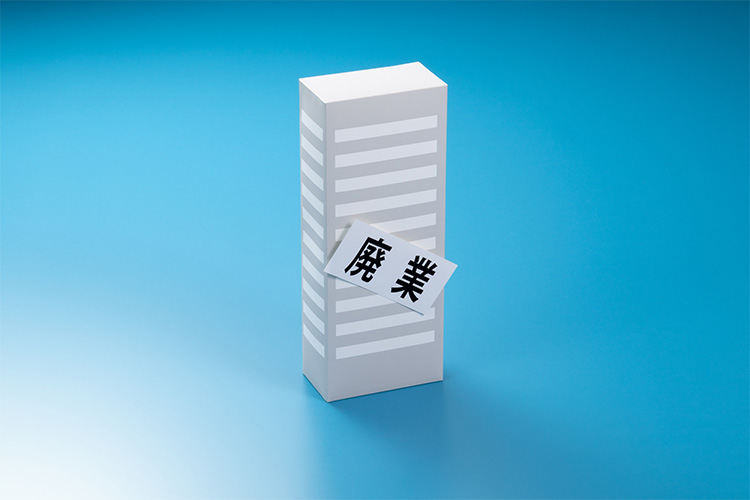
投稿日:2025年01月09日更新日:2025年06月06日
会社をたたむ費用はいくら?廃業手続きの流れも解説
- #ニュース・コラム
- #廃業
- #ニュース・コラム
- #廃業

投稿日:2024年06月03日更新日:2025年06月06日
M&Aのディールとは?一連のプロセスと成功につながる4つの秘訣
- #ニュース・コラム
- #M&Aの流れ
- #ニュース・コラム
- #M&Aの流れ
#カテゴリ・タグ一覧
まずはお気軽にご相談ください
※秘密厳守でご対応します。
幅広い業種の案件を成約させたプロの
メンバーが丁寧にご対応します。