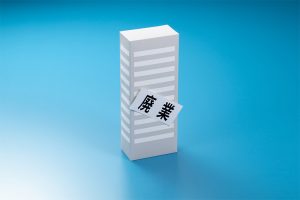逆さ合併とは?メリットや実施する際の仕訳・会計処理のポイントを紹介

逆さ合併とは、事業規模の小さい会社が存続会社、大きな会社が消滅会社となる吸収合併を指します。
「繰越欠損金の控除」を適用できる点や、合併差損の発生を避けられる点などが実施する主なメリットです。ただし、目的によっては逆さ合併と認められないことや、株主から反対されうることには注意しましょう。
このコラムでは、逆さ合併の意味や仕訳・会計処理のポイントについても解説します。
逆さ合併とは
逆さ合併とは、事業の規模の小さい会社が存続会社、より大きい会社が消滅会社となる合併を指します。大きい規模の会社が存続会社となるのではなく、より小さい会社が存続会社となる点が逆さ合併の主な特徴です。
ここから、合併の意味や、逆さ合併と逆取得の違いについて解説します。
そもそも合併とは
合併とはM&Aの手法で、複数の会社をひとつに統合することです。消滅会社の権利・義務を存続会社が引き継ぐ吸収合併と、新たに設立した会社が消滅会社の権利・義務を引き継ぐ新設合併があります。
合併の主なメリットは、シナジー効果を発揮できる点や権利・義務をまとめて承継できる点などです。一方で、手続きに手間や時間がかかるなど、デメリットもあります。
なお、逆さ合併は、より小さい会社が存続会社となり、大きい会社の権利・義務を引き継ぐ吸収合併です。
逆さ合併と逆取得の違い
逆さ合併と逆取得は、本来異なる概念を持つ言葉です。ただし、状況によっては逆さ合併が逆取得に該当するケースもあります。
逆取得とは、株式を交付した会社と、会計上の取得会社が一致しない取引のことです。たとえば、逆さ合併でより大きな会社が小さな会社側の株主に株式を交付することにより、小さな会社側の株主が発行済株式の過半数を取得して支配権を得ると、逆取得に該当します。
吸収分割や株式交換、株式交付も逆取得が発生しうるM&Aのスキームです。該当する状況については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の第8条第36項に規定されています。
逆さ合併を実施するメリット
逆さ合併を実施する主なメリットは、以下のとおりです。
- 「繰越欠損金の控除」を適用できる
- 合併差損の発生を避けられる
- 規模の小さい会社のブランド力を活用できる
各メリットについて、解説します。
「繰越欠損金の控除」を適用できる
繰越欠損金の控除を適用できる場合があることが、逆さ合併のメリットとしてあげられます。欠損金を繰越控除できる期間は、原則として10年です。
繰越欠損金の控除とは、前期までに所得で税務上の赤字を計上している会社が、当期の黒字所得と相殺できる制度を指します。欠損金額が生じた年度に青色申告書の確定申告書を提出し、その後連続して確定申告書を提出している会社が当期に黒字を計上している場合に、適用の対象です。
存続会社が赤字会社の場合、条件を満たすと繰越欠損金の控除を認められます。その結果、逆さ合併を選択することが節税につながるでしょう。
なお、かつては適格合併として認められなかった逆さ合併が、2019年の税制改正に伴い適格要件を満たすことで繰越欠損金の控除など税制上の優遇措置を受けられるようになりました。具体的な適格要件は、「100%支配関係(完全支配関係)のあるグループ内での再編」「50%超えの支配関係のあるグループ内での再編」「共同事業を実施するグループ外企業との再編(支配関係がない)」によって異なります。
参考: 国税庁「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」
合併差損の発生を避けられる
合併差損の発生を回避できる点も、逆さ合併を選択するメリットとしてあげられます。
合併差損とは、消滅会社の負債が資産を上回る状況や存続会社が消滅会社に交付する金銭の帳簿価額が承継する純資産額よりも大きい状況で合併することで、存続会社に損失が発生することです。たとえば、より大きな規模の会社が存続会社、小さな会社が消滅会社となる合併を選択することで損失が発生する場合に、あえて逆さ合併にすることで合併差損を回避できることがあります。
規模の小さい会社のブランド力を活用できる
規模の小さい会社のブランド力を活用できることも、逆さ合併のメリットです。
たとえば、規模が小さくても知名度がある会社を消滅会社として吸収合併すると、顧客にアピールする機会を減らす可能性があります。規模が小さくても、より多くの人に知られている社名・ブランド名を残す逆さ合併をあえて選択すれば、引き続きブランド力を活かした営業を進められるでしょう。一方で、規模が大きく知名度もある会社を消滅会社とする場合、ブランドや信用力を失う点に注意が必要です。
逆さ合併を実施するデメリット
逆さ合併を実施することのデメリットは、以下のとおりです。
- 目的によっては逆さ合併と認められない
- 上場廃止の可能性がある
- 株主から反対されることがある
それぞれ解説します。
目的によっては逆さ合併と認められない
目的によっては、逆さ合併と認められないことがある点がデメリットです。あからさまな節税目的の場合、国から適格合併と判断されず、通常と同じ税制が適用される可能性があります。
適格合併と認められるためには、存続会社と消滅会社の支配関係に応じて、金銭等不交付や継続保有要件などを満たさなければなりません。専門的な知識が要求されることもあるため、専門家への相談を検討した方がよいでしょう。
上場廃止の可能性がある
逆さ合併を選択することにより、上場している存続会社が上場廃止となる可能性がある点もデメリットです。
より規模の小さい会社が上場している一方で大きな会社が非上場の場合、上場を目指してあえて逆さ合併を実施することがあるでしょう。しかし、証券取引所による審査で基準に適合しないと判断されると、上場廃止となります。裏口上場を防止することが、基準が設けられている主な理由です。
株主から反対されることがある
株主から反対されることがある点も、逆さ合併を実施するデメリットです。
一般的に、逆さ合併を進めるためには、消滅会社・存続会社の株主総会においてそれぞれ特別決議で承認を得なければなりません。そのため、自身の株式保有割合が変動することに不満を持つ一定数の株主たちが反対すると、逆さ合併を実施できない可能性があります。
関連して、逆さ合併の手続きを進めるにあたっては、株主総会の調整や会計処理などの手間がかかることもデメリットです。
逆さ合併の手続きの流れ
ここからは、消滅会社と存続会社に分けて逆さ合併の手続きの流れを紹介します。
消滅会社の手続きの流れ
消滅会社が逆さ合併を実施する際の主な流れは、以下のとおりです。
- 取締役会の決議後に合併契約を締結する
- 合併の前日までに株主総会の承認を得る
- 債権者保護手続きを進める
- 株主から株式買取請求や新株予約券買取請求などがある場合は対応する
- (合併効力発生)
- 解散登記をする
- 財産などの名義変更手続きをする
債権者保護手続きとは、合併などの組織再編を実施する際に、債権者が異議を述べる機会を一定期間確保することです。官報公告への掲載や債権者への個別催告などによって、合併の事実を伝えたうえで、異議のある債権者に対して弁済しなければなりません。
存続会社の手続きの流れ
存続会社が逆さ合併を実施する際の主な流れは、以下のとおりです。
- 取締役会の決議後に合併契約を締結する
- 合併の前日までに株主総会の承認を得る
- 債権者保護手続きを進める
- 株主から株式買取請求がある場合は対応する
- (合併効力発生)
- 変更登記をする
- 財産などの名義変更手続きをする
消滅会社は合併時に解散登記の手続きをするのに対し、存続会社は変更登記をすることなどが異なります。
逆さ合併を実施する際の仕訳・会計処理のポイント
逆さ合併を実施する際の仕訳・会計処理のポイントについて、消滅会社・存続会社に分けて解説します。
消滅会社の場合
消滅会社が逆さ合併で存続会社の株式を受け入れる際に、個別財務諸表における株式の原価を合併時の損益を考慮せず株主資本相当額で算定することがポイントです。一方、消滅会社と存続会社の連結財務諸表を作成する際は、消滅会社の資産・負債を時価で取得したものとして計上します。
連結財務諸表を作成する際には、株主の持分比率が低下することを考慮して事業の移転時価から株主資本相当額を引いた金額を資本準備金として計上することもポイントです。
存続会社の場合
存続会社は合併時の個別財務諸表において、消滅会社から引き継ぐ資産・負債を適切な帳簿価額で算出します。また、消滅会社が保有している存続会社の株式を自己株式で計上する点もポイントです。たとえば、X社(消滅会社)がY社(存続会社)の2,000万円相当の株式を保有している場合、Y社の個別財務諸表に「自己株式 -2,000万円」を計上します。
なお、共通支配下の取引の場合は、個別財務諸表で「のれん」が発生していなくても、連結財務諸表において「のれん」が発生することがあるため注意しましょう。
まとめ
逆さ合併とは、事業の規模の小さい会社が存続会社、より大きい会社が消滅会社となる吸収合併を指します。「繰越欠損金の控除」を適用できる、合併差損の発生を避けられるなどのメリットがある一方で、逆さ合併が認められないことや株主から反対されることがある点がデメリットです。
また、逆さ合併を進めるためには、債権者保護や登記などの手続きを進めなければなりません。そこで、スムーズに実施するために専門家に相談することが大切です。
人気の記事

投稿日:2024年08月23日更新日:2025年06月06日
地位承継とは?意味や継承との違い、使い分けなどを解説
- #ニュース・コラム
- #スキーム
- #ニュース・コラム
- #スキーム
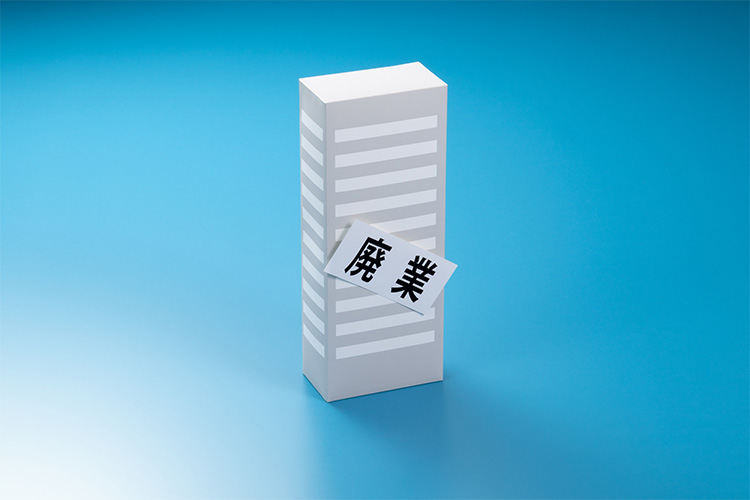
投稿日:2025年01月09日更新日:2025年06月06日
会社をたたむ費用はいくら?廃業手続きの流れも解説
- #ニュース・コラム
- #廃業
- #ニュース・コラム
- #廃業

投稿日:2024年06月03日更新日:2025年06月06日
M&Aのディールとは?一連のプロセスと成功につながる4つの秘訣
- #ニュース・コラム
- #M&Aの流れ
- #ニュース・コラム
- #M&Aの流れ
#カテゴリ・タグ一覧
まずはお気軽にご相談ください
※秘密厳守でご対応します。
幅広い業種の案件を成約させたプロの
メンバーが丁寧にご対応します。